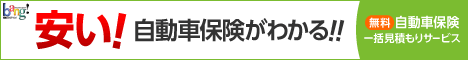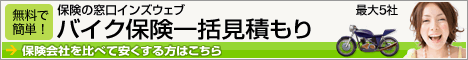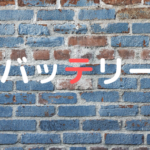いよいよ2段階の教習も中盤に入ってきました。
今回は、大型二輪教習(普通二輪免許持ち)の2段階3時限目で実施する交通の状況及び道路環境応じた運転などについてお伝えしたいと思います。
各教習所で違いがあるのは、コースの規模や四輪教習との兼ね合いで教習項目の進め方に違いがあるということです。
ここでは、わたしが勤務していた教習所での教習項目の進め方で説明をさせていただきますので、お通いになられている教習所での進め方と多少異なる点が発生するかも知れませんが、その点についてご了承いただいたうえでご活用いただけますと幸いです。
各教習項目の注意点やコツについては、参考にしていただけるところがあると信じてお伝えさせていただきます。
車間距離について
この時間では最初に30メートル先に設置している看板を見てもらい『何メートル離れているように見えますか?』と質問をしていました。
多かった回答は、15メートルくらいと答えてくれる方が多く、なかなか30メートルと言ってくれる方がいなかった事を印象深く覚えています。
バイクから降りた静止している状態なので、いつもとは違う状況だからと言われることがありましたが、わたしは走行しているときの方が、距離の読み取りは難しくなるような気はしました。
教習生さんの答えを聞いて感じたことは、前車との車間距離が狭くなっている可能性がとても高いということでした。

それは、街中での走行を見ていても感じることがあります。
だから、車間距離のことについて再確認をして欲しいという気持ちが強くなりました。
車間距離の取り方
安全な車間距離は60キロまでの速度ならマイナス15することでわかるようになっています。

例えば、60キロなら15をマイナスして45メートルが安全な車間距離です。
70キロ以上の場合は速度の数字分をメートルに変えるだけでよいので、70メートル、100キロなら100メートルでよいと教科書に書かれています。
この方法で覚えておけば良いのですが、前の車との距離を正確に言い当てることは難しく、正直言ってわたしも自信がありません(汗)

参考にして下さいと言ってお伝えていたことは、秒で計る車間距離の取り方です。
やり方ですが、前車が信号機などの目標物を通過した後に、自車が何秒後に通過するか?をカウントすることで安全な車間距離を取る方法です。
例えば、先ほどの60キロを例にしますと、60キロで走行していると1秒間に17メートル進みます。
17×3秒で51メートルの車間距離を取ることが出来ます。
教科書では60キロでの安全な車間距離は45メートルとなっていますから、概ね同じ数値となります。

これなら、いちいち頭の中で計算しなくても前車と3秒空けると覚えておけば良いのと、実際に使うときにもメートルを目測するよりは、かなりやりやすく精度も向上します。
この3秒を基準に雨で路面が濡れていたら5秒に変えるとか、ツーリング後半で少し疲れてきたから4秒にするなどして応用することで更に便利に活用することが出来ます。
あとは、大型二輪車は重たい分、普通に考えると普通二輪よりも停止する距離が長くなるわけですから、普通二輪のときよりも車間距離を広くしておくことが大切だと考えます。
後続車の状況も確認
交通の状況については、前方や横だけではなくて後ろの状況も把握することが含まれています。
だから、どれくらいの頻度でミラーを見ていますか?という質問をしていました。
返ってくるお言葉が『あまり見ていないです』とか『進路変更するときぐらい』にしか見ていないと言われる事が多かったです。
実は、知っておいて欲しいことがありまして、現在、交通事故で多いのは『追突事故』が突出して多くなっています。

なんと、全事故の約40%を占めています。
とても多いのです!!

追突をしないように気を付けることがもちろん必要ですが、追突をされないようにすることも必要になります。
後続車の状況を確認することで、追突されることを防止できるわけではありませんが、後続車がとってくれている車間距離を確認することで、危険な状況を早く察知することが出来ます。
例えば、ミラーで見たときに後続車の車間距離が見るからに狭いと感じた場合で、信号が黄色に変わった場合にそのまま交差点を通行するという選択をすることで、追突防止を図ることができます。
また、ミラーで見たときに後続車のドライバーがスマホを見ながら運転をしていることが確認できたら、追突防止のために道を譲って先に行かせたり、ブレーキ灯を早めに点灯させて後続のドライバーに注意喚起をすることも可能となるわけです。

普段、あまり後続車を気にすることがなく『ミラーを見る回数が少ないかも』と心当たりがありましたら、事故予防を兼ねてこれを機にミラーを見る回数を増やしていきましょう。
自由走行
バイクの教習は大型二輪も普通二輪も路上教習がありませんので、ツーリングや仕事で行うことがある目的地を設定して走行するという経路設計の練習ができません。
実は、四輪の教習では路上教習で地図を広げて自分で経路の設定して走行する練習時間があります。
二輪の教習でその変わりになるのが、『自由走行』という練習です。

自由走行なので自由に走行してもいいように聞こえますが、そこは指導員がお題を出します。
例えば、スラロームと一本橋とクランクの3つを走行するコースを設計してくださいとか、必ず1番目にスラローム、2番目に一本橋、3番目にクランクというように、走行する順番を指定する場合もあります。

15分くらいの時間を使って練習してもらっていました。
覚えてきている検定コースと少し違う走行順番を変えるだけで、ウインカーを出す時機が遅れたり、忘れたり、道が気になってしまい確認が甘くなったり、完全に見ていなかったりします。
ここで、経路設計の大切さを確認してもらっていました。
スマホがあるので、今さら経路設計なんて必要なのか?と思われるかも知れませんが、通信環境が悪くてスマホが使えない場合やスマホナビの状態が悪くて道に迷いこともあるので、迷ったまま走行すると周りが見えす、危険な物を発見することが遅れたり、対応が遅れたりします。
だから、まず安全な場所で止まって経路の確認をすることを強調してお伝えしていました。
検定コース
この時間も検定1、2コース両方を使って練習することになります。
わたしが指導していた教習所のカリキュラムでは、この時間以外でしっかりと検定コースを走行できる教習時間は、残りたったの1時間しかありません。
教習生のみなさんにプレッシャーがかかることをわかっていながら、この時間で完璧に検定コースを走行できるようにしましょう。と声高々に言っていました。

後々に困る顔を見たくないために本心から言っていたことでした。
運転に集中できるように頑張って検定コースを覚えましょう。
さいごに
安全な車間距離については、前車と『3秒の時間』を確保することで簡単に取ることが出来ます。

車でも車間距離を取ることはもちろん大切です。
バイクの場合は車間距離の取り方が狭かった場合、以下のような危険性があります。
前車が急ブレーキをかけたときにライダーが冷静にブレーキ操作ができず、パニックブレーキになってしまうと追突をしなくても、自ら転倒する可能性が出てきます。
もちろん、ABSのブレーキ装置が付いていれば転倒を回避することも出来るかも知れませんが、急ハンドルをきったためにバランスを崩して転倒することもあります。
あとは、驚いて身体が固まってしまい何も出来ないまま追突してしまう事も考えられます。
車では、追突することはあっても転倒することはほぼありませんが、バイクは転倒があると考えると、安全な車間距離を取ることは必須であると強く感じています。
次回は、2段階4時限目に行う教習内容についてお伝えしたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
今回の内容参考になりましたら幸いです。もとゆき
教習や検定のお悩み相談を無料でやっています。
Twitter(@moto2019)DMください。お待ちしております。
★ 操作性にすぐれたグローブです。