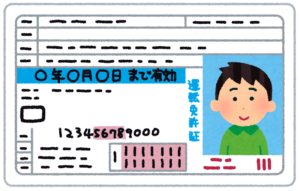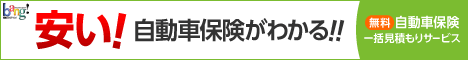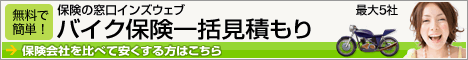わたしは教習所で20年間指導員をしていました。四輪車、二輪車、検定(試験)、学科などの教習をしていました。高齢者講習についても長きに渡り業務の担当をしていました。今回は、高齢者講習で使用する車についてお伝えしたいと思います。これから、高齢者講習を受講される方の参考になりましたら幸いです。よろしければお付き合いください。
教習車
高齢者講習で使う車は教習所で使っている教習車を使うことになります。車種は教習所によって違いはありますが、トヨタのカローラ、マツダのアクセラなどいわゆるセダンと言われるタイプの車になります。また、マニュアル(MT)ではなくオートマチック車(AT)を使うことになります。受講者の方からよく言われたのは、『自分の車を使えないか?』という事でした。普段、軽自動車しか乗っていないので不安に思われていた方がとても多かったです。
S字コース、クランクコース
高齢者講習では実技講習で教習所内を走行することになります。ちなみに路上を走行することはありません。
教習所内のみです。
わたしが高齢者講習を担当していたときに、車の大きさの違いで
受講者の方が苦労されていた点についてお伝えします。
昔から四輪免許を取得するときに通行していたS字、クランク(屈折)コースを高齢者講習でも通行することになりますが、
この2つのコースを通過するときに苦労されている方を多く見てきました。
それは、普段軽自動車を乗られている方からすると教習車の車体が大きいため(正確に言うと前輪タイヤと後輪タイヤの取り付け位置が違うため)に、
内輪差の影響で後輪タイヤが縁石に乗り上がったり、コースから後輪タイヤが脱輪することがありました。
これを防止するためには、普段軽自動車を乗られている方でしたら、S字やクランクコースで曲がるときに、
ハンドルを回す時機を少しだけ遅らせる事と走行位置を曲がる方向から離れて外側を通行することで、脱輪を防止することが出来ます。
車庫入れ
高齢者講習では、教習所内のポールが設置された場所で後退で車庫入れを行います。この場所で受講者の方によく言われたことは、『軽自動車と違い後ろの感覚がわからない』でした。よく言われました。セダンタイプの車では、トランクの部分が軽自動車よりも長くなっているので、後ろに下がり過ぎてポールにぶつかる方が多かったです。ちなみに車輪止めはありませんので下がり続けると必ずポールに当たってしまいます。だから、あまり下がらないように意識をしておいてください。どこまで下がるというのも決まっていませんので、ある程度下がったらギアをパーキングにして、ハンドブレーキをかけて下さい。そうすると指導員が道順を言ってくれます。
車輪止めがありませんので、
とにかく後ろに下がりすぎないことです。
さいごに
高齢者講習の実技を担当しているときによく言われた言葉が、『普段は軽(自動車)に乗っている』でした。おおげさではなく5千回は聞いた記憶があります。教習所でも軽自動車を用意することが出来れば受講者の方の不安を少なくすることが出来ますが、現実的には車を何台も用意することは教習所側として難しいところがあります。だから、今後も教習車を高齢者講習で使用するという今のスタイルは変わることはないと考えます。高齢者講習の実技は試験ではありませんが、タイヤが乗り上がったり、ポールにぶつかることは気持ちよいものではありません。なので、今回お伝えさせていただいた、S字コースやクランクコースでは後輪タイヤが乗り上がらないようにハンドルを回す時機を早くならないように気をつけて、車庫入れで下がり続けてポールにぶつからないように気をつけて走行してみてください。今回の内容が参考になりましたら幸いです。最後までお読みいただきましてありがとうございました。もとゆき