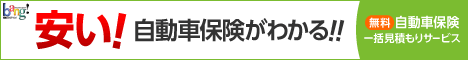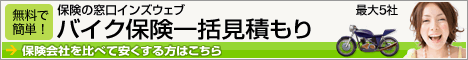四輪教習(普通免許)で1段階を修了すると、修了検定と仮免許学科試験を受けることになります。
指導員時代によく質問をいただいたのが、仮免許を取ったらすぐに路上に行くのですか?という言葉でした。
この疑問についてお伝えしたいと思います。
よろしければお付き合いください。
結論 すぐ路上に出ます
早速、結論になりますが、すぐに路上に出て練習を行います。
ただし、路上に出る前に日常点検を行うので、5分くらいは点検することになります。
それから、最初に教習所内のコースを準備運動で1周くらいは走行するかも知れませんが、教習開始から7分後くらいには、路上に出ています。
路上で練習することが教習の項目となっているので、路上走行がメインとなります。
教習生さんの反応は、こんなに早く路上に出るとは思っていない方が大半でした。

心の準備が整う前に路上でハンドルを握っているという感じです。
そのような状況で、助手席からたくさんのことをアドバイスしても、聞いてもらうことは難しかったので、シンプルなアドバイスを心掛けていました。
初路上の注意点
次は、教習生さんの立場でアドバイスさせていただきます。
初路上で意識してやりたいことは、怖いと思いますが頑張ってアクセルを踏むことです。
もちろん教習所によって、路上に出てからの最高速度に違いがありますので、教習所内で走行していた速度と変わらない場合もあれば、いきなり50キロの速度を出さないといけない場合もあると思います。

速度を出すことで大きなメリットがあります。
1つは、自然と目線が先に向くようになります。
速度が上がると先の状況を早く見たいという心理になり、近くを見ていた教習生さんも、顔を上げて先を見るようになることが多かったです。
これに、プラスして具体的にどこを見ればよいか?をお伝えしますと前車がいれば、前車を見るようにしましょう。

前車がいなければ、次の信号を探すようにしてください。
これを意識することで目線を先に向けることができるようになります。
もう1つは、早い速度からのブレーキ感覚をつかむことができることです。
教習所内では、30キロ以下の速度で走行するケースが多く、40キロ以上の速度からのブレーキ操作を行うことはなかなか出来ません。
その状態で、路上で40キロや50キロを出すと、どれくらいブレーキを踏んだらよいのか?
わからない状態になります。
この状態をいち早く解決するために、頑張って速度を出してブレーキをかける回数を増やす必要があるわけです。
どれだけ、指導員がわかりやすい言葉でブレーキの掛け方を説明しても、実際に右足でブレーキペダルを踏んで、実感しない限りは上達することはありません。
チャンスがあれば、何回も40キロや50キロの速度からブレーキを掛ける練習をした方が、早く慣れることができますので、頑張ってアクセルを踏んでいきましょう。
初路上までに準備しておきたいこと
次に余裕があれば初路上教習までに準備しておきたいことをお伝えします。

準備しておきたいことは、初路上のコースを確認しておくことです。
確認といっても、バイクや自転車で事前に走ることではありません。
教習所から配布されている(ない場合もあります)教習コースや検定コースが記載された地図を使って確認することです。
確認しておきたいことは、右折や左折が何回くらいあるのか?複数の車線がある道路なのか?を調べておくことで、所内の教習で習ったことを活かしてイメージトレーニングすることができます。
更に、可能であれば初路上のコースをグーグルマップを使って確認しておくと準備、万全となります。

グーグルマップの写真機能を使うことで、より具体的に確認することができます。
車線の数や規制速度の標示を見ることができるので、走行コースのより詳しい情報を知ることができます。
これをするだけでも大きな安心感を得ることができます。
ひと手間ありますが、実践する価値は大いにあると感じています。
さいごに
指導員をしていたときに、『仮免許を取ったら、すぐに路上に行くのですか』は、本当によくご質問いただいた言葉でした。
すぐに路上に行きますよと返答すると、大きな声で『ええ~』と言われていたことを
覚えています。
確かに、1段階最初の時間では、カートレーナーという機械で教習を受けたり、実車であっても、教習車が止まっている状況で指導員が時間をかけて説明しています。
だから、2段階になった仮免許を取ったらすぐに路上へ行くことは、指導員としてはあたり前に感じていても、教習生さんからしたら驚くべきことだったかも知れないと今、記載していて感じました。
この記事をお読みいただき、仮免を取ったらすぐに路上に行くことをお知りいただいたので、少しは心の準備ができることで、初路上教習の緊張を緩和するお手伝いが少しでも出来ていれば幸いです。
免許取得頑張ってください。応援しています。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
今回の内容が参考になりましたら幸いです。もとゆき